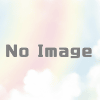【宮城県】仙台城(再訪)

2025年8月16日
お盆の真っ只中、2024年2月以来の仙台城に訪城。
仙台城は言わずと知れた、伊達政宗が築城した仙台藩62万石の本拠地。
仙台城に来た理由は、令和3年と令和4年に起きた福島沖地震によって崩落した、本丸北西石垣の積み直しが完了したとの情報があり、まだ見ぬ仙台城の石垣を見るためにやってきました。
何度もこのブログで仙台城を書き込んでいるので、同じことを書いてしまいますが悪しからず。

まずは近くに車を駐車して、三の丸の水堀の前を通って大手門跡へと向かいます。
高い土塁で囲まれた場所には三の丸がありました。仙台城の遺構は少ないと言われていますが、この水堀と土塁は立派です。

大手門跡。
綺麗に積まれた切込接の高石垣の上には土塀があります。ちなみに、この土塀は仙台城の中で唯一の現存建築物になります。

土塀の脇には国内屈指の巨大な大手門があり、国宝に指定されていましたが、残念ながら仙台空襲の際に焼失しました。
大手門は復元されるのが決定しており、調査が進められています。
以前来た時にはなかった石積みを確認しました。これは復元に関わる工事の一環なのでしょうか。

そして、土塀の反対側には脇櫓。
こちらも空襲で焼失しましたが、昭和42年に復元されています。

脇櫓はバリケードがあって近寄る事ができませんでした。
大手門復元の際に、この脇櫓も新しく復元される予定で、現在発掘調査中です。

脇櫓と奥の土塀のの間に大手門があり、2038年に復元される予定。
大手門がどれだけ大きな門であったが分かります。
しかし、復元完了が13年後は長い!その時にワタクシは50歳を超えています。

大手門跡から本丸には整備された山道を登ります。
その途中には中門跡があります。
まず、この中門跡に感激!前回来た時は崩落したままで、ブルーシートが掛けられて一切復旧工事がされていませんでしたが、いつのまにか綺麗に復元されていました!

道路は公道になってしまいましたが、90度に折れ曲がる喰違いはまさに城があった証。

中門は道を遮るように二階建ての櫓門が道を塞いでいました。

絵図も残っており、中門は老朽化のために大正時代に解体されてしまいました。
解体の際に作成された平面図もあるので復元して欲しいものですが、一般車もバスも普通に通る公道になっているので、現実的には復元は難しいと思われます。

中門の石垣の上。絵図を想像して立ってみます。
2003年に地震で石垣の一部が崩れ、解体復旧工事が行われた際、多数の金箔瓦がここから出土しています。
金箔瓦は一部の大名しか使用する事が許されなかったので、仙台藩は外様ながら有力な藩であったことが伺えます。

中門を抜けると本丸北壁石垣を見る事ができます。
この芸術的な石垣は仙台城のシンボルでもあります。緩めの勾配から上部ではほぼ垂直にそり返る、曲線美。

隙間なく積まれた切込接の石垣。
地震で崩落した際に、石垣の中から古い時代の石垣が出てきたことで、伊達政宗時代の石垣は現在見える石垣の中に眠っている事が判明しました。

大迫力の高石垣は圧巻の17m。
山城でこれだけの高い石垣を、この技術で積んだ城はなかなか見る事ができません。

仙台城には建築物が残って無いので、観光で来た人のなかには残念に思う方が多いようです。
しかし城マニアにとってはこの石垣だけでも満腹になる程、素晴らしい。

本丸北西の石垣。
地震で崩落したことで、昨年も一昨年も修復作業のため、バリケードで完全に入ることができませんでした。

綺麗に修復されています。

時代の異なる積み方も見ることができます。
左側は隙間なく加工された石材を使用していますが、右側は自然石をそのまま使用しています。

無骨な野面積みと、ここまで整った切込接の石垣の切り替えは他で見たことはありません。

東北には石垣の城が少ないのが現実で、東北の石垣の名城といえば会津の鶴ヶ城と岩手の盛岡城です。
しかし、仙台城も劣らない程、石垣を多用した城です。

酉門跡。
築城期の石垣も一部現存しており、幾度も地震で崩落し修復されています。
酉門の石垣も、時代が異なる石の積み方をしています。現在は立ち入り禁止となっています。

大手門の模型。まだまだ先ではありますが、かつての姿を取り戻すことを楽しみにしています。

こちらの模型は本丸詰門跡。
現在は護国神社の鳥居が建っています。
天守を持たない仙台城でしたが、本丸には天守クラスの三重櫓が四基も上がっていました。
高さ17mの本丸北壁石垣の上にあった三重櫓となる艮櫓の復元の話が進められていましたが頓挫。
新しく櫓を復元するとなると、杭を岩盤まで打ち込むので、石垣の中に眠る伊達政宗時代の石垣を保存することを優先。復元は断念されました。

本丸にある伊達政宗像。
逆光のコントラストがよりカッコ良さを引き出してくれました。北の大都市、仙台の礎を築いた伊達政宗は、仙台の人々の中に生き続けています。

本丸からの眺望。
大都市と仙台平野、太平洋を望むことができます。
姿は変わってもこの景色を伊達政宗も見ていたと想像するだけで、一味違ったエモーショナルな景色に見えてきます。

上から見た本丸北壁石垣も、圧倒的なスケールで迫力があります。

本丸には仙台城の石垣の構造を見ることができます。
隙間なく綺麗な積まれた石材の後ろは長く伸びていて、栗石と呼ばれる小さな石材を詰め込んでいます。
隙間のない石垣は排水が出来ず、水圧を直接受けて崩落するので、裏には栗石で隙間を作って水圧を分散しています。

本丸大広間跡。
仙台城を象徴する建築物で、当時は障壁画や飾金具で煌びやかに装飾された大規模建築物でした。
豊臣秀吉が京都に築いた聚楽第と同じく、桃山様式の御殿でした。
明治の廃城令によって破却、大広間を含む仙台城の建築物の多くが取り壊されました。

本丸からの沢門跡を抜けて、三の丸方面へ下ると清水門跡があります。
本丸北壁石垣に比べて、ゴツゴツとした野面積みが印象的。

三の丸にあった巽門。
二重の櫓門でしたが、仙台空襲によって消失。当時の写真が残っていますが、大手門に次いで立派な門でした。
現在は礎石が復元整備されています。

今回のもう一つの目的は、仙台城の移築城門を見ること。
宮城県知事公邸には仙台城の寅門が移築されています。
仙台城からはやや離れていますが、車だと10分かからず到着。鯱も上がっており、城門らしい四脚門。

大正時代に、第二師団長官舎の正門として移築されました。
仙台城のどこにあった門かは明らかになっていませんが、廃城令と火事による消失、空襲で建物が残っていない仙台城にとっては貴重な遺構です。
何度も来ているのに、来るたびに新しい発見があったり、季節や天候によって同じ城でも見え方が変わる。
それも城の魅力の一つですね。だから、同じ城でも何度も行ってしまう。
今回は、本丸西側の石垣と中門の復元した石垣を見ることができて大満足です。
何年もかけて石垣の復元に携わってくださった方々には本当に感謝です。
これも一つの歴史として、何十年、何百年後も語り継がれるはず。