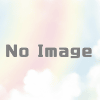【兵庫県】篠山城

2025年8月9日
本日のラストは兵庫県の篠山城で締めくくり!
朝から福知山城→丹波亀山城→余部丸岡城→篠山城の長距離移動を慣行!
余部丸岡城から篠山城までは車で約1時間で、篠山城に到着したのは14時半頃。篠山城はアクセスを考えると、是が非でも今回にまとめて攻略しておきたい城でした。
篠山城は1609年に丹波篠山盆地に築かれた近世城郭。
彦根城、名古屋城、姫路城、伊賀上野城と同じく、徳川家康が大坂城包囲網として天下普請で築城しました。
1600年の関ヶ原の合戦から1614年の大阪の陣までの期間は、豊臣家と徳川家の軍事緊張が高まり、日本では築城ラッシュとなりました。
車で京都の亀岡市から篠山城に辿り着くまで、丹波の山々を越えてきましたが、本当にこんなところに城があるの?と疑ってしまうほど山に囲まれています。

篠山城の外堀は広いところで幅40m、深さ4m。当時の姿をそのまま残しています。
篠山城は輪郭式の平城で、中央に本丸と二の丸、本丸と二の丸を囲むように三の丸があり、さらに三の丸を巨大な水堀で囲んでいます。
現在、三の丸には駐車場や学校があるので、城郭の遺構としては二の丸からとなります。

二の丸、本丸は内堀で囲まれ、強固な防備体制となっています。
橋を渡れば二の丸。当初、北廊下橋には屋根付き長屋形式の建物が橋の上にありました。

北廊下橋の先には表門跡の石垣が残ります。

北廊下橋から見た左側。二の丸の石垣と複雑な水堀形状。
そして、篠山城の特徴といえる犬走り。
水堀から石垣が立ち上がるのではなく、犬走りという石垣の前に設けられた、平らのスペースから石垣が立ち上がっています。
犬走りは本来、字の如く犬が通れるほどの幅くらいなのですが、篠山城の犬走りの幅はかなり広め。

北廊下橋から見た右側、二の丸の石垣。こちらも、幅の広い犬走りが設けられています。
大突貫工事だった篠山城は、工事スピードを早めるために、資材を置くスペースとして幅広の犬走りが設けられました。
確かにこの幅の資材置き場があれば、工事効率は格段に上がると思います。

至る所に刻印石を見る事ができ、200種類2000個の刻印石があります。
さすが天下普請で造られた城。
豊臣恩顧の大名にあえて造らせることで、財力を奪い、さらには全国の大名を呼ぶ事ができると豊臣家への牽制の意味もありました。
ちなみに、総奉行は池田輝政。縄張り奉行は築城名人の藤堂高虎。全国15ヵ国の大名が呼び寄せられました。
現代ですと総奉行は統括現場所長、縄張り奉行は監理設計士のようなイメージでしょうか。

表門を抜けると、90度折れ曲がって中門跡となります。
当時は多聞櫓で囲まれていた事を想像すると、かなり厳重な門であったと考えられます。
もし多聞櫓があれば彦根城の佐和山門のようだったかもしれませんね。
かなり石垣の高さがあるので、威圧感がすごいです。

振り返っての中門跡。
90度に折れ曲がって、さらに90度折れ曲がる喰違い虎口。青空とのコントラストが最高です。

中門を抜けると鉄門があり、いよいよ二の丸です。写真は振り返っての一枚。
現在は城内管理用の冠木門が建っていますが、ここには櫓門形式の城門が立ちはだかっていました。

鉄門を抜ければ大書院の入口となります。
大書院脇には直径2m、深さ22mの井戸があり、現在に至るまで枯れた事がないそうです。

二の丸には大書院、小書院、中奥御殿、奥御殿、台所など、多くの御殿建築が建ち並んでいました。

明治の廃城令で多くの建築物が破却されたものの、大書院だけは残されました。
全国で御殿建築が残っている城は、二条城、高知城、掛川城、川越城のみ。
そして篠山城の大書院も貴重な現存御殿建築の一つでしたが、昭和19年1月6日の夜に焼失してしまいました。
現在の大書院は2000年に復元。

二の丸 大書院の内部。
二の丸には幾つもの御殿がありましたが、大書院は歴代藩主による公式行事などに280年間使用された書院造の建築物となります。

虎の間には有名武将の甲冑が飾られています。

上段の間。
格式が高く、一段高くなった場所は位が一番高い城主のみが触れる場所。大書院は26m×28mで二条城の御殿を参考にして造られました。

二の丸にある、もう一つの井戸。

井戸は今も綺麗な石積みを覗く事ができます。

二の丸の南東側は一段高くなっており、本丸跡となります。
本丸跡は現在、神社となっています。

本丸を囲む石垣。
今は石垣が残るのみですが、石垣の上には長屋形式の多聞櫓が上がっていました。

本丸南東の隅には天守台があります。
天守は建てられる事なく、隅に平櫓が上がっていました。
天守を建てる計画はありましたが、超実戦型の篠山城は想像を超える堅城だったので、天守は不要と徳川家康が判断したとも。
工期一年の大突貫工事だった篠山城でしたが、次の名古屋城築城を控えていたので、天守は造らなかったとも。
他にも天守を造らなかった理由は諸説あります。

天守台から見た東側。
東側の三の丸は篠山城学校とグラウンドになっています。

南側三の丸。
手前側には内堀、奥には大きな土塁が残っています。

北側三の丸。
現在は駐車場になっていますが、この日はお祭りの準備のために業者さんが懸命に設営作業をしていました。

一度、北廊下橋から三の丸に戻り、内堀の周りを歩いてみます。
二の丸北側の高石垣と、上には大書院の屋根が見えます。

二の丸西側の石垣と内堀。隅には櫓が上がっていました。

南側、本丸の石垣は特に圧巻です。奥の角は天守台で、一際高い石垣になっています。

天守台は高さ17m!幅は東西19m、南北20mでほぼ正方形。
美しく芸術性を感じる高石垣ですが、本来の目的は鉄壁の軍事要塞。

再び北側の二の丸石垣を見るために移動。
ほぼ正方形の均整のとれた城郭ですが、至る所にせり出してクランクしている箇所があります。これこそ防御システムの一つで、正面からだけでなく側面からも十字に攻撃できるようにするための工夫です。

北廊下橋と表門の石垣。
隅部は算木積みで、その他は自然石を生かした野面積み。篠山城の石垣は江戸時代に何度か修理を行なっているようです。

個人的にはこのアングルショットが好き。
北東は屏風折れのようになっていて、迫力ある高石垣の隅石を同時に見る事ができます。

手前の北側石垣ですが、石垣の積み方が特徴的。
加工された石が、半円状に落とし積みで形成されているように見えます。この辺りは築城当初よりも、後の時代の技術が盛り込まれています。
篠山は京都と山陰、山陽を結ぶ交通の要衝だったので、重要な位置付けとして天下普請で築かれました。しかし、この一体は小山ながら大半が硬い岩盤だった為、人力で岩盤を切り崩して現在の城の形にするには困難を極めました。
それでも8万人を動員して完成させた篠山城は、全国でもトップクラスの堅城となりました。
初代城主は徳川家康の実子の松平康重、以降は松平三家で8代、青山家6代が城主を務めました。

篠山城の特徴で、見どころの一つが馬出!
馬出は城内の入口となる虎口を防備する為、そして兵を駐屯して応戦するための防御施設。近世城郭で馬出を多用している城は珍しく、特に西国の城としては篠山城のみかもしれません。
篠山城には大手馬出、東馬出、南馬出が設けられていました。南と東は形が残っており、大手馬出は埋め立てられています。写真は東馬出。
馬出も水堀で囲まれており、城に入るにはこの馬出を通過しない限り先には進めない構造でした。
外堀を何気なく歩いていたら、馬出を発見して感動しました!

東馬出は現在、東馬出公園として整備されています。
戦国時代に武田氏と北条氏が多用したのが馬出。まさか、この馬出を近世城郭に多用するとはさすが実践型の軍事施設。
武田氏と徳川家康が奪い合った諏訪原城では、徳川家康が改修した際に馬出を造っており、今でも巨大な三日月型の堀を見る事ができます。

最後に、篠山城から歩いて15分ほどの場所に、河原町妻入商家群があり、江戸末期からの面影を残した街並みを散策する事ができます。
この日は4城目ということもあり、かなり疲弊していましたが、この街並みを見たら歩きたくなります。
ゆったりとした時間が流れていて、まるで別世界のよう。
18時半に亀岡市でレンタカーを返却して、電車で京都市内に向かいました。かなり充実した1日となりました。
京都市内に一泊し、翌日は市内の観光をする予定。