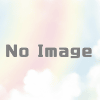【京都府】丹波亀山城

2025年8月9日
朝一に福知山城を登城した後は亀岡市にある、丹波亀山城に向かいました。
福知山城も明智光秀が築城した城でしたが、丹波亀山城も明智光秀が築いた城として有名です。
丹波攻略の拠点として1577年頃に明智光秀は亀山城を築城しました。
15809年には丹波国を拝領した明智光秀は、城下町の整備と領国経営に着手。
そして、2年後に本能寺の変が起きます。
ちなみに本能寺に出兵する際は、この丹波亀山城から出陣したとされています。

亀岡駅を出て、駅前の大通りを真っ直ぐ進むと奥に森が見えます。その森の中に丹波亀山城はあります。
駅から近いので、交通のアクセスも良好です。

駅前通りを突き当たると、明智光秀像と鯱が二つ。
やはり、この街も明智光秀の影響というのは今でも残っています。

当時の水堀は、南郷公園として親しまれています。

立派な水濠で、この堀沿いを歩くと亀山城に繋がる道に辿り着くことができます。

亀山城跡には大正時代から、宗教法人 大本本部があり管理しています。
入り口を通過すると中央部に大本の受付があるので、そこで簡単な入城の手続きを行います。
受付では入城料300円を支払い、注意事項を聞きます。
丁寧に資料を元に亀山城について教えて下さります。ちなみに、御城印もこちらで購入できます。

受付を終えて入城すると、早速内堀の跡と石垣を確認できます。
亀山城は明智光秀が築いた後、1610年に天下普請によって大改修が施されました。

廃城令後は石垣は崩され、建築物も破却され荒れ果てていましたが、大正8年に大本がこの土地を入手してから、残っていた石垣を掘り起こして積み直して復元。
しかし、戦時中の宗教弾圧によって再び石垣も破壊されてしまいます。
戦後に再び積み直されて今に至ります。

天下普請らしく、亀山城の石垣には多くの刻印石がありましたが、現在は唯一この堀跡の前の石垣に刻印石が残ります。

受付でもらったルート図を元に本丸跡へと向かいます。
至る所に石垣は残っています。
足を切り出す際にできる矢穴の跡も見ることができます。

本丸の近くには井戸も残っています。

そして本丸の石垣に到着!
自然石を使った美しい高石垣!

受付の方に聞いたのですが、名城の石垣を多く手掛けた、石工集団の穴太衆の技術は現在も継承されており、この石垣の検証をお願いした事があるそうです。
なんと下から15段目くらいまでは明智光秀時代の石垣と判明しました。

情報を知ってから見るとすごく感慨深いもので、明智光秀の凄さを感じる事ができます。

下は緩やかな勾配ですが、上部はほぼ垂直。
この曲線美は1600年以降の築城ラッシュで多用されるようになりました。

本丸は現在、聖域とされ禁足地となっています。
木が生い茂っており分かりづらかったのですが、本丸には大イチョウの木があり、明智光秀が築城の際に植樹したと伝わっています。

最後に明智光秀時代に積まれた本丸石垣下部を見て、来た道を戻ります。

江戸時代にはこの本丸には、築城名人で有名な藤堂高虎が築いた五重の層塔型の大天守が上がっていました。
古写真を見てもその凄さが伝わります。
さらに現在は堀の一部しか残っていませんが、三重の堀で城下町ごと囲んだ総構えの巨大城郭でした。
市内にはいくつか移築の建築物も残っています。
しかし、やはり福知山城に続いて亀山城にも明智光秀の息吹はこの街に今も残り続けていると感じました。
かなりハードなスケジュールですが、亀岡駅近くのレンタカーで次は再び明智光秀に関わる城跡に向かいます!