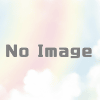【兵庫県】明石城(再訪)ライトアップ

2024年2月5日
東大阪の現場視察、堺市での設計打ち合わせが15時半頃の終了した為、急いで兵庫県の明石城に向かいました。
昨年に明石城には一度訪問しているのですが、均整の取れた現存の三重櫓に圧倒されすぎて、他の見どころを完全に見落としてしまった為、再度訪問しました。
ちなみに、明石城は個人的に好きな城のトップ3に入るほどお気に入り。
大阪駅から神戸線に乗って不覚にも到着が17時30分頃。
既に外は薄暗かったのですが、予定通り決行です!
時間がないのでJR明石駅から門を抜けてストレートに本丸方面へ向かいます。
写真撮影も省略しました。

まずは左手には三重の坤櫓。
櫓とは思えぬほど風格があります。
こちらは現存の櫓で天守閣が無かった明石城の天守代用とされた櫓です。

続いて右手には巽櫓。
こちらも現存の三重櫓。
この二つの櫓が本丸の両隅にあり、迫力が満点すぎて前回はつい櫓を見るのに夢中になりすぎました。

こちらが主郭への入り口です。
奥に見えるのは二の丸、さらに奥には東の丸があります。
前回、そちらには全く行かなかったので後悔しておりました。
明石城の定番かもしれませんが、この角度からのショットが好きです。
約5mの石垣の上に、15mの石垣が乗り、さらに約13mの櫓が上がっているので、グランドラインから見ると30m以上を見上げる事になります。
この数値だけでも、明石城の凄さがお分かり頂けると思います。
こちらは本丸の櫓の反対側、東の丸の石垣。
この上には二重の櫓が上がっていました。

奥から東の丸→二の丸→本丸と連郭式となっています。
張り出した石垣が東の丸で、引っ込んだ石垣が二の丸。

主郭部に向かう門跡。
ここを抜けると左手が本丸、右手が二の丸になります。

東の丸から見た二の丸と本丸の写真。
この時、既に暗くなりつつあります。

二の丸跡。
今は門の跡と広場のみとなっています。
上から眺めた眺望。
現在、下には明石公園として広場や野球グラウンドになっていますが、以前は御殿などが広がっていました。
城郭面積は姫路城よりも大きかったそうです。
さすが将軍徳川秀忠による天下普請で築かれた城。

東の丸入り口からの城門。
枡形虎口となっていて、石垣のみが残ります。
この先には薬研堀があり、土橋で城外に繋がります。
そちらは、暗すぎて写真を撮ることができませんでした。

二の丸と東の丸を繋ぐ城門跡。
形から推測するに、長屋のような建築物がこの石垣の上にあったと思われます。
二の丸から見た本丸。
現存櫓の反対側から見た景色で、本丸がかなり張り出しているのが分かります。
ここから見た石垣も迫力があり凄まじい。
下に降りる道はあるのですが、やはりこちらも暗すぎて断念。
写真は加工しているので明るく見えますが、この時間で既に18:00でしたのでかなり暗いです。

本丸の巽櫓。
巽櫓と坤櫓の間は土塀を復元しており、展望台となっています。
ここからの景色も素晴らしい。
奥には淡路島と明石海峡大橋が見えます。

登城した逆側から降りて本丸の下周りを歩きます。
本丸の石垣。
こちらにも当時は櫓がありました。

本丸の石垣と奥には天守台があります。
右手は稲荷曲輪が広がります。
以前も通っている道なのですが、ちゃんと調べてから周ると見どころが多い城跡だと改めて実感します。

このショットもお気に入り。
天守台、坤櫓、タワーマンション。
ライトアップも綺麗で、城漆喰の櫓が昼とは違った顔を見せてくれます。
比べると天守台が巨大なのが分かります。
ちなみに、明石城の天守台は熊本城並みの大天守が上がるほどの規模。
坤櫓だけでも迫力あるのに、ここに大天守があったらと、想像せずにはいられません。



到着した17時半からちょうと1時間が経過したことで完全に暗くなり、再び戻って同じアングルからのショット。
さっきとは全く別物に見えます。
ライトアップの明石城。カッコ良すぎます。
2000年に復元した土塀は高さ2.3m、長さ96m。
阪神大震災を乗り越えて現代に生き続ける名城。

明石駅からのショット。
この写真を見ていただくと分かるのですが、櫓がある本丸に目がいきがちですが、とても横に広い城郭なのが分かると思います。
暗くて逆側を見ることができなかったの
結果として次の日も行く事にしました。
明石城の歴史等に関してはそこで触れたいと思います。