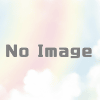【京都府】福知山城

2025年8月8日
二条城を堪能後は、用事を済ませて福知山市に向かいました。
今回は二条城と福知山城に行くことが最大の目的で、京都駅からは特急で約1時間半程。
大河ドラマの麒麟がくるを見てから、明智光秀推しとなったワタクシにとっては、福知山城は絶対にコンプリートしたい城でした。
続日本100名城に選定されている、京都府を代表する城です。
福知山城は丹波攻略の拠点として、明智光秀が築城し、城下町も整備しました。
到着は完全に夕方。

電車の中から撮影した写真。
夕暮れが近かったので、なんとなくエモーショナルな一枚になりました。

この日はホテルにチェックインしてからライトアップを見て、8月9日の朝一からゆっくり見て回りました。
様々な撮影スポットを巡りましたが、おそらく電車の中からの写真が最終的には一番ベストスポットと感じました。
ちなみに、夕飯はビジネスホテル近くの「喜ぶん屋 偶達」さんで夕飯。
リーズナブルなのに料理が美味しく、メニューも豊富だったので大満足な福知山市の夜を過ごすことができました。

8月9日の朝7時45分にホテルをチェックアウト。
ききょう通りを抜けて城に向かいます。遠くには福知山城が綺麗に見えます。
桔梗といえば明智光秀の家紋。
由良川の氾濫でこの街はいつも苦境に立たされていたが、明智光秀がこの福知山城を拠点としてから
治水工事を行い、年貢を免除するなど領民から大変慕われたと伝わります。
天下の謀反人と呼ばれた明智光秀ですが、この街の方々にとって明智光秀は敬愛される存在であり続けました。
それは今でも間違いなく残っていると感じました。

福知山線の線路沿いを歩いて向かうと、天守の上階が見えてきます。
昨日のライトアップの際は暗くて怖かったので、大通りから城に向かいましたが、
城の西側も是非見ていただきたい。

本丸西側の石垣。
明智光秀の時代の石垣ではないかもしれませんが、高石垣が福知山城の本丸を支えています。

割と大きめ石材が使われており、複雑に鋭角に曲がっています。
真下で見ることはできないのですが、近づくことができるので是非この圧巻の石垣も見逃さないで欲しいですね。

福知山城は現在、東側より入城することができます。

初代城主、明智光秀以降は城主が度々変わり、最終的には朽木氏が長いことこの地を納めます。
しかし、街も城も割と明智光秀一色です。
天守台周辺の標高は約40m。

最初の坂道を登り切ると、本丸に続く階段があります。自然石を積み上げた野面積みと階段の勾配に沿った、登り石垣が美しい。

釣鐘門を抜けると本丸の天守に到着です。
連結した大天守と小天守、複合の櫓などが複雑に接続された天守。

天守への入り口は埋形式で、石垣の中に埋め込まれた門より入城します。

本丸の入り口となる釣鐘門。
非常に変わったこの門は、絵図を元に復元されました。
城門では稀な楼門形式で高さ7.3m。上層部に釣鐘が吊るされていたとも言われています。

本丸には豊磐井(とよいわのい)という井戸が残っています。
その深さはなんと50m!城郭の本丸にある井戸の中では日本一の深さ。
そしてこの井戸には二の丸の北側にある横穴と通じていると言い伝えが残っています。

福知山城の天守台。
福知山城といえば、やはりこの無骨に積み上げられた天守台です!

多くの転用石が使用されています。
現在、使用されている転用石は181個。
天守台内部の調査で出土したのは321個。
まさに転用石の宝庫です!

天守を含めた福知山城のほとんどの建築物が、明治初期に取り壊されました。
残ったのはこの石垣と、銅門番所のみ。
しかし、1986年に復元。現在は築城者である明智光秀を深く知ることができる資料館となっています。

隅石にも転用石が巧みに使用されています。
築城は1579年ですが、天守台石垣は明智光秀の時代から残っているとされています。

福知山城で貴重な現存建築、銅門番所。
本来は二の丸の登城路にあった番所で、市役所あたりにあったと言われています。
現在、二の丸は削り取られて住宅地となっています。

銅門は福知山市内の正眼寺に移築。
なぜ、この銅門が取り壊されることがなかったのかは不明らしいのですが、間違いなく現代では貴重な遺産であります。
ちなみに、この銅門番所は一度天守台に移築されていたそうですが、天守と小天守の復元に上がって本丸に再移築という形になりました。

石垣を見ると左側の前面に飛び出した石垣の真ん中に、斜めのラインが入っています。
右側は明智光秀時代の石垣で、天守も今よりコンパクトだったと考えられています。

天守構造は三層四階の望楼型。
古写真などは無いことから、正確な外観復元というわけでは無いようですが、望楼型の天守は見る角度によって顔が大きく変わるのでやはり魅力的!

これだけの転用石を使用している城は、福知山城以外には奈良の大和郡山城くらいでしょうか。

小天守側には珍しい跳ね出しを見ることができます。

中の資料館。やはり、明智光秀です!
丹波平定の軌跡などを学ぶことができます。
ご存知の通り、織田信長は天下統一目前で本能寺の変によって最後を迎えますが、逆に明智光秀がいなければ織田信長は天下統一への道を辿ることは無かったのではないかと個人的には思っています。
それだけ明智光秀は武力・知力・作法、教養も兼ね備えた武将でした。

天守最上階から見た景色。
明智光秀が治水工事をした由良川も見えます。

福知山市は山々に囲まれた盆地で自然に溢れています。
縄文時代から人が住んでいて、交通の要衝として重要視されてきたエリア。
明智光秀が丹波平定の拠点としたのは、そういった理由もあるのかもしれません。

小天守の北側?の石垣はかなり高く、本丸内部から見る天守の姿とはまるで異なります。

こちらは本丸北側?の石垣。
東西南北の感覚が分からなかったのですが、おそらくらこちらが北側になるのかなと思います。
天守台よりも時代が後に積まれた石垣なのか、同じ野面積みでも技術が格段に進歩しているように思えます。

高さも圧巻なのですが、勾配も急でとても美しい曲線美です。

死角を減らすために、石垣は複雑に折れていて防御機能を高めています。
土塀は復元ですが、やはり土塀があると城の雰囲気はだいぶ変わりますね。

福知山城の前には由良川の支流の法川があり、堀の役目を果たしています。
川に架かる橋は昇龍橋。対岸と高低差がある場所に架けられた橋なので、まるで龍のような形をしています。
天守に登っていく龍のようで、カッコいいですね。

福知山城の写真スポットでもある伯耆丸公園周辺から撮影した一枚。
昇龍橋とは逆側になります。
正面からも撮影できるのですが、やや斜めの方が個人的には良き。

前日に行ったライトアップの福知山城。
昇龍橋から撮影した天守。

本丸の高石垣も幻想的で綺麗です。

本丸からの天守。
城内は暗かったので、1人での散策は少し怖かったのですが、やはりこの高ぶった瞬間を逃すわけにはいかないのです。

福知山城一帯が暗いので、あまり歩き回ることはできなかったのですが、夜でも市役所の駐車場からは綺麗に天守が見えるのでオススメです。
初めて行った福知山城でしたが、明智光秀について改めて深く知ることができました。
そして、明智光秀の息吹は400年を超えても、この街に根付いていると実感。
10時半に再び特急に乗り、明智光秀が築城した城へと向かいました。