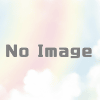川越城@埼玉県
2023年10月1日
小江戸として観光客に大人気の川越市。
江戸時代にタイムスリップしたような、蔵の街並みを楽しむ事ができます。
オシャレなお店なども多いので若い方にも大人気のエリアです。
しかし、忘れていけないのは城下町という事。
当然、川越市には城がありました。
城好きの人なら皆知っていますが、小江戸というワードが先走って、城の存在を知らない方が多くいます。
城あっての城下町。
川越城は日本100名城になっていますので、城好きの方なら絶対に抑えておきたい城。
当時から天守閣は無く、江戸幕府の重臣達が代々居城としていて、北の守りとなる重要拠点でした。
江戸時代の主な城主は酒井家、松平氏。
現在は本丸御殿の一部が現存しています。日本で本丸の現存は、高知城と川越城の二棟のみ。
貴重な城跡になります。

川越城は本川越駅から、ゆっくり歩いて15分ほど。
街並みを楽しんで歩けばあっという間の時間です。

蔵づくりの町並み、大正ロマン通りが小江戸と呼ばれるメイン通りです。
ワタクシは行きはメイン通りを外して一本隣の筋から川越城を目指しました。

メイン通りを外しても蔵づくりの建物が数多く存在しています。
むしろ、メイン通りは人が多すぎるのでこちらの方が、じっくり見る事ができて良いかもしれないです。

お店もレトロな感じで、雰囲気がいいんですよね。

浴衣で歩きたい街並み。
中央図書館前の、細く住宅街の路地から向かいます。

川越高校の近くに曲輪門跡があります。
目の前の林には御嶽神社があり、昔はそこが富士見櫓がありました。

こちらが櫓跡地。
富士見櫓の規模は不明ですが、三重で15m×14mと言われています。
天守閣のなかった城なので、おそらくこの富士見櫓が天守の代わりだったと思われます。
三重の富士見櫓という名前だと、江戸城の富士見櫓を連想します。
江戸城も天守が焼失してからは富士見櫓が天守代用でした。

富士見櫓跡からの景色。
昔は富士山も一望できるほどだったらしい。

続いて本丸御殿に到着です。
玄関の大きな唐破風。
まるで寺院の入り口のような造り。

玄関の間口は13間(23m)もあります。

彫刻も彫られており、重厚感のある唐破風。特別な意味合いを持つ建物だったことが見てとれます。
そして各所、垂木の小口が白く塗られています。
これはデザイン製なのかと思っていましたが、後から調べたら浸水や木材の割れを防ぐ役割があるそうです。

川越城の縄張り。
今ある本丸の御殿はほんの一部であって、実際はかなり大きな城郭だった事がわかります。
明治期に川越城は取り壊され、堀は埋められ今では当時の1/8の面積しか残っていません。

中は大広間、家老の詰め所などを見る事ができます。




美しい日本庭園もあり、平和な時代を象徴しています。

御殿の中には小さな展示室があり、瓦も飾られています。
徳川家の家紋がカッコいいですね。

昔ながらの木造の内装を見ると、祖父の家を思い出します。

武蔵国の中心にあった川越城。
藩庁も置かれて、政治の中心地でした。
こんな感じで政治が行われていたんですね。


釘隠。
長押や扉に打った鍵を隠す目的で使われていた装飾。
よく天守閣にも使われています。



現存の大広間は36畳!

立派な襖絵も残っています。

堀も埋められたので現在はその姿を見る事ができません。
唯一、中ノ門堀がほんの一部のみ残っています。



堀がしっかりと残っています。
残念ながら堀の遺構が残っているのは全体でこの一部のみ。
堀の上には狭間を設けた土塀が張り巡らせていたそうです。

メインの蔵通りは観光客で大混雑。
歩道も狭い為、立ち止まって写真を撮るのは難しいですね。

川越市のシンボル時の鐘。
創建された江戸時代初期から、暮らしに欠かせない時を知らせてきました。
川越城は天守閣や櫓が残っていないので、やや寂しい部分も感じますが、本丸が残っているのはやはり貴重です。
城下町の小江戸と併せて楽しむのがやはり良さそうですね。
昭和通りにあるレトロな食堂、シブヤ。中華〜洋食まで揃う老舗。
昔ながらのオムライス。
このオムライスが食べたくなるんです!ステンレスの皿も最高です。
詳しくは↓↓