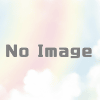【静岡県】興国寺城

2025年2月8日
東海道本線で巡る城の三城目は静岡県沼津市にある興国寺城に向かいます。
2月7日:清洲城→大垣城→掛川城ライトアップ
2月8日:掛川城→諏訪原城→興国寺城
諏訪原城で長く滞在したので、やや時間は押していましたが、ほぼ計画通り。
興国寺城は北条氏旗揚げの城として有名です。
戦国時代の小田原北条氏の祖となる伊勢盛時(北条早雲)が今川氏より与えられて城主となったので、小田原北条氏はここから始まったとされています。
北条と名乗ったのは二代目氏綱からです。よって、小田原を拠点とした北条氏の祖は北条早雲ということになります。
しかし、鎌倉幕府の北条氏とは別のルーツですが、実際は全く関係が無かったというわけでは無いようです。
北条早雲と興国寺城の関係については、専門家は疑問を呈していますが、事実として興国寺城は今川・北条・武田・豊臣・徳川など領地争いの境界となった城であるということ。この一帯を勢力下に納めるには必要不可欠な城であったと思われます。

東海道本線からの富士山。
諏訪原城がある金谷駅から、興国寺城の最寄りとなる原駅までは約1時間20分。
知らない街並みを見ながら電車で旅をするのも良き。
原駅に到着したのは13時半頃。
原駅から興国寺城までは約2.7km。歩くと40分以上かかります。
バスが運行していますが、今回は時間の都合上、行きはタクシーを利用しました。駅前にはタクシー乗り場もあるので、すぐに乗車できます。

タクシーだと10分も掛からないで、興国寺城の登城口に到着です。
国の指定史跡で続日本100名城に選定されています。

あたり一面は広大な敷地で、登城口あたりは三の丸跡になります。
立ち入りはできませんが、土塁が残っています。

三の丸から一段高くなっている曲輪が二の丸。
三の丸には柱穴群が発掘調査で見つかっているので、いくつかの建築物が並んでいました。

二の丸と本丸。
広大な空き地が広がりますが、こちらも中に入ることはできません。二の丸と本丸の境目となる段差の中央あたりには本丸虎口跡が発見されました。

本丸の巨大な土塁。まずはこの土塁の大きさに衝撃を受けます。
土塁は本丸をコの字で囲んでいます。

特に本丸の正面にあたる土塁は、推定14mの巨大な土塁です
本丸には穂見神社があり、続日本100名城スタンプはここで押すことができ、パンフレットもここにあるので、見ながら周るのがお勧めです。
穂見神社の脇から土塁の上に登る道が整備されています。

一際高い本丸正面の土塁の上には天守台があり、石垣の一部を見ることができます。
令和2年、令和5年に天守台石垣の発掘調査が行われ、幅20mで高さ5mと確定されました!
調査後に埋め戻されていますが、この石垣の下にもさらに石垣が積まれています。
時代としては豊臣秀吉が天下統一した以降のものと推測されています。

天守石垣の脇を通って土塁の上に向かいます。

天守跡では礎石が見つかり、建築物が2棟建っていました。
しかし、瓦が出土しなかったことから、イメージする壮麗な天守閣は無かったそうです。

天守台からの景色。
手前から本丸、二の丸、三の丸と連郭式になっていて、奥に立ち並ぶ住宅の先には駿河湾が広がります。当時は三の丸あたりは水濠があり、水堀の役割を果たしていました。
海と山、そして東海道という交通を掌握できる恵まれた立地もあってか、土造りの中世城郭ながら1607年まで興国寺城は存続します。

大土塁の隅は西櫓台跡となっており、そこから眺める本丸西側の土塁もまた良き。
城郭で土塁は基本中の基本ですが、ここまで大きく分かりやすい土塁は初めて見ました。

本丸正面の大土塁の上は整備されているので、安全に散策することができます。

本丸東側の土塁。
上から見ると完全に山の尾根の様になっています。

本丸東側土塁の裏側は細い道になっていて、間近で巨大な土塁を眺めることができます。

北曲輪と天守台を分断する大空堀。
驚愕の規模を誇る大空堀は堀幅20〜30m。高さも本丸側は20mは超えているであろう巨大な空堀になっています。

堀底を歩くことができます。
左側が本丸、右側は北曲輪。左側奥のメタボリックのお腹のように張り出していますが、その上が伝天守台です。
堀底はクネクネと食い違いになっています。

堀底の西側は絶壁になっており、再び食い違いになります。
そして、写真ではニつしか見えませんが三つの謎の洞窟があります。
戦時中の防空壕なのでしょうか。何の説明書きもない洞窟なので、やや不気味ではあります。

洞窟のある食い違いを進むと、巨大な空堀は岩盤を切り崩した、切り通しとなって空堀の出入口となります。
是非、堀底を歩いた際は見て頂きたいポイント。空堀を抜けると一般道に出るので、北曲輪を目指して右に進みます。

東海道新幹線が低い位置を走っていて、橋が架かっているので、興国寺城は新幹線の線路によって分断されているのではないかと思われます。
線路沿いを道なりに登ると、北曲輪の入口があります。
北曲輪でも空堀が発掘調査で発見されていますが、復元せず埋め戻されているのでしょうか。確認することができませんでした。

北曲輪から見た天守台!
大きさも際立っているのですが、出丸や砦の様に張り出しているので、全方位から攻撃できるように設計されています。

北曲輪から見た大空堀。
こちらから見た方が、より空堀の規模が分かりやすいですね。
スケール感が分からなくなりますが、堀底に人がいたら豆粒みたいな感じです。大空堀は堀底がV字の薬研堀。

再度大空堀に戻り、少し気になった場所に向かいます。
本丸東側の土塁裏から階段で下って大空堀の堀底に行けるのですが、大空堀が薬研堀に対して、降りてすぐの場所は箱堀のように底が広がっています。
空堀はそのまま斜面に沿って三の丸方面に続いているのですが、堅堀のようになっていたので、気になって写真を撮りました。

上からのショット。
2列並んだ堀が下まで続いています。立ち入ることができないのですが、堅堀のようにも思えます。
自分の知識不足か、もしくはそもそも遺構なのかも不明ですが、興国寺城は全体的にポテンシャルの高さを感じる城でした。
間違いなく中世城郭の楽しさや魅力を教えてくれます。
後は御城印を購入しに行きます。興国寺城を出たのは15時半頃。
興国寺城にはガイダンス施設などが無いので、御城印は地元の幾つかのお店で販売されています。
ワタクシは興国寺城から歩いて5分ほどの、お茶屋の野崎園さんで購入しました。

御城印ついでに、大寒波到来の日でしたが抹茶のモナカを購入!

中はアイスなのに抹茶の苦味もあって、サッパリして美味しいモナカ!
帰りは歩いて原駅に戻ります。

広がる草原。
ひんやりとした気温ですが、空気が澄んでいて素晴らしい時間を過ごしました。
帰りは時間に余裕があるので、原駅まで歩いて戻ります。
歩きながら改めて感じたのは、道がひたすら真っ直ぐなこと。
原駅までバイパスが横切っていますが、それ以外は真っ直ぐに進むことができる道ばかり。
これが当時の街割とは限りませんが、左右綺麗に道が交差するので、当時の名残の可能性もあるのかなと感じました。
戦うために造られ、実際に戦いを繰り返してきた中世の城というのは、造りの工夫全てに意味があり、生死を分ける緊張感もあります。
残された遺構からメッセージを読み解き、イメージしながら城を歩くのが中世城郭の楽しみ方。
大雪の影響で帰りの新幹線は50分ほど遅れていましたが、天気も含めて全てが、ほぼ計画通りに進んだ二日間でした。計画通りいくと達成感があります。
これもまた楽しみ方の一つ。