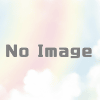【広島県】三原城

2025年9月6日
朝イチで広島城を周った後は、山陽新幹線に乗って三原城へと向かいました。
三原城は三原駅にある続日本100名城で、広島駅からは新幹線だと25分で到着します。広島県に来たのであればセットで攻略したいお城です。
三原城は毛利元就の三男、小早川隆景が1567年に築いた城。
1580年から10年かけて整備。その後は福島氏が改修し最終的には東西約900m 南北約700m 32基の櫓 14の城門を有する、巨大な城郭に変貌を遂げました。
瀬戸内海に面した地に築かれ、軍港としての機能も備えていました。一国一城令後も三原城は存続し、広島城の支城としての役割を果たしました。

新幹線のホームを降りると、ホームの窓を覗くと目の前には天守台が!
突然現れた天守台にまず度肝を抜かれます。
水堀に浮かぶ天守台をこのアングルで見ることは他ではできません。三原駅は三原城の本丸にあり線路が貫通しているので、この大迫力のロケーションを見ることができます。

新幹線ホームを降りると、甲冑や絵図などが飾られており、駅構内が資料館と化しています。

駅構内のイラストパネル。
三原城は海に浮かぶ城郭だったので浮城とも呼ばれていました。

三原城天守台には三原駅のコンコース内から入城できます。
天守台は水堀に囲まれているので、駅構内からしか入ることができません。朝6時から夜22時まで開いています。

駅構内から階段を上がると、東側の天守台石垣が目の前に現れます。
水堀には鯉が優雅に泳いでいます。天守台の高さは、およそ15m!
三原城には天守は立てられませんでしたが、かなり大きな天守台を見ることができます。

天守台の上は現在広場となっており、地元の方がのんびりとした時間を過ごしていました。
天守台には多門櫓が配され、隅には櫓がありました。
しかし、大正期の古写真では姿を消して天守台石垣が残るのみでした。

天守台から見た後藤門跡の石垣。
絵図には、こちらに後藤門という喰い違いの門がありましたが、現在は道路になっています。
石垣は推定復元をされていて、実際はもっと高い石垣で、さらには道路の方まで石垣が伸びていました。

天守台の上から見た山陽新幹線の線路。
見事に城郭内部を突き抜けています。笑
線路を境に城郭遺構は分断されてしまいましたが、本来は堀も石垣も港の方まで伸びていました。
天守台を降りて、駅内にある三原市の観光協会に寄って続日本100名城のスタンプを押印。御城印もこちらで購入。

今度は水堀の外を歩いてみたいと思います。
観光案内所から天守台水堀には線路の下を通り抜けます。そして、線路の高架下に立派な石垣を見ることができます。
天守台は水堀で囲まれて近づけないので、高架下のこの石垣が一番近くで見ることのできるスポットとなります。
隅は綺麗に整形された算木積みとなっています。

天守台東側の石垣。
東側は福島正則によって積まれた石垣になります。この巨大な天守台は、広島城天守の6基分の大きさ。

東側石垣の隅石。
短辺・長辺の直方体の石材を交互に積んだ、算木積となっています。上から下まで一定の、やや緩やかな勾配。

一方で北西の石垣。
隅石はゴツゴツとした石材を使った重ね積み。西側の石垣は小早川隆景によって築かれた石垣で、東側に比べると勾配が急です。

東側に比べて西側のほうが一つ一つの石材が大きく、自然石を使った野面積み。
西側のほうが古い石垣ですが、個人的には曲線や積み方は、西側のほうが美しいように思えます。

北側から見た天守台。真後ろには新幹線の線路が見えます。
右側が小早川隆景が築いた石垣で、左側が福島正則が築いた石垣。
右側がやや上部が反り返るような曲線を描き、左側は一定の勾配で上部に伸びています。近世の取れた正方形な天守台のように見えますが、よく見ると左右で勾配が異なっているので、二つの異なる技術を同時に楽しむことができます。

西側の高架下は石垣が破壊されています。
当時は天守台からずっと港にかけて本丸石垣が長く伸びていました。
今回は周り切れませんでしたが、三原港の方に行くと船入櫓跡と中門跡の石垣が残っています。その他は、ほぼ市街地化によって残っていません。
しかし、逆によく天守台だけはここまで綺麗に残ったなという印象。
良くも悪くも山陽新幹線によって破壊された本丸ですが、新幹線ホームが天守台を見るには最高のスポットになっています。徹底的に破壊された城も多くある中で、駅とドッキングした新しい形の城でした。
天気が良かったこともあり、最高の写真を撮ることができました。