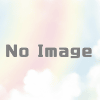【京都府】二条城

2025年8月8日
今日から3日間、京都で一人旅。
お盆真っ盛りですが、相変わらず京都は外国人が多い。
当然、この街には魅力的な神社仏閣が多くあり、人々を魅了し続けます。
しかし、ワタクシはこんな京都の街でもお城を巡ってしまいます。
京都を代表する城といえば、天下の江戸幕府を象徴する二条城です。
東京から始発で8時過ぎに到着!
タクシーで二条城に向かいますが、意外と距離があ
り2000円をお支払い。
8時45分に開城となりますが、10分前くらいに到着。外人さんが先に何人か並んでいましたが、入城する頃には後ろに多くの方が並んでいました。

二条城はいつも観光客で混雑しているので、開城前に並んで、人が映らない写真を撮るのが最大の目的でした。
メインゲートとなる東大手門も人がいないので、バッチリ綺麗に撮れています!

東大手門と東南隅櫓。
東大手門は重要文化財に指定されていて、さすが徳川将軍家の城。
大きさも、装飾美も別格です。
こんな華やかな櫓門は他で見ることができません。

内部から見た東大手門。
東大手門は立派な二重の櫓門形式で、現在の門は1662年頃の建築と考えられています。
築城当初も現在と同じ二重の櫓門でしたが、寛永の二条城行幸時に天皇を二階から見下ろさないように、高麗門に建て替えられたそうです。

東大手門の抜けると番所があります。
現存する番所は珍しいので、貴重な遺構です。

東大手門を背にして左側が順路になります。
二の丸は築地塀で囲まれていて、二の丸に入るための唐門があります。
まず、お城で築地塀を採用しているのは大変珍しく、他で見ることはできません。
唐門も築地塀も寺院建築で多く見られるので、なんとなくお城でありながら京都らしさを感じます。

唐門と二の丸御殿。
日光東照宮のような、桃山様式の華やかな装飾と芸術的な彫刻。
二の丸御殿の正門で、天皇の寛永行幸に備えて残念に建てられました。

二の丸内部からの唐門。
四脚門形式で当時は瓦葺でしたが、明治の修復の際に檜皮葺に葺き替えられてしまいました。

とてもお城とは思えない豪華絢爛な門。
長寿を意味する松竹梅に鶴、聖域を守護する唐獅子など彫られています。

二の丸御殿は二条城の最大の見所と言っても過言ではありません。
近世城郭には政治や城主の住まいとなる御殿が必ず城内に建てられていました。
しかし現在は、全国で御殿建築が現存しているのは4城のみ!
◯川越城(埼玉県)
◯高知城(高知県)
◯掛川城(静岡県)
◯二条城(京都府)
今回で全ての現存御殿を見ることができました。
その中でも二条城の二の丸御殿は国宝に指定されており、徳川政権の象徴のような豪華絢爛な御殿でした。

内部は撮影禁止。御殿内の各部屋は華やかな金色の障壁画で、全面彩られています。
絵師は最高技術を誇った狩野派が総力を上げて仕上げました。
徳川幕府が京において威厳を示した城だということを実感することができます。

続いて二の丸庭園。
二の丸御殿の大広間、黒書院、白書院から鑑賞できるように設計されています。
庭園など風情のセンスがないワタクシですが、二の丸庭園は広いし、巧みに石が使われているし、きっと凄いんだろうなーとは感じました。

二の丸庭園の脇を抜けて、本丸に向かいます。
本丸は内堀で完全に囲まれていて、東橋と西橋でのみ繋がっています。

東橋と重要文化財の本丸櫓門。
非常に質素で珍しい造り。扉は全面が銅板張り。
これも天皇を見下さないように、二階部分の窓を無くしたのでしょうか。

本来、城とは防衛施設なので、橋を渡ってくる敵を迎え撃つために、櫓門の二階には格子窓を設けているのが一般的ですが、正面に窓がないのが特徴的。

防御面の観点からすると、あり得ない造りですが、これは二条城の存在価値が防衛だけでなく、権威やシンボル、対面の場としての役割も大きかったと考えられます。

本丸櫓門を進むと高石垣を抜けます。
この辺りは圧迫感があって城らしさを感じます。

本丸の西南側の隅には天守台が残ります。
当時は伏見城から移築した五重六階の天守が上がっていましたが、1750年に落雷で消失。

天守台から見た内堀と桃山門。

天守台から見た西橋と西虎口。
家に帰ってから写真を見返したら、天守台の最頂部が石狭間になっていることに気づきました。
これは大阪城や江戸城でも見ることができます。

天守台上から見た土蔵。
城内に10棟あった土蔵の内、3棟が現存。本丸内堀沿いの南側と北側に均等に配置されています。

本丸御殿。
創建時の本丸御殿は1788年に消失しました。
現在の本丸御殿は、江戸後期に京都御所の北に建てられた桂宮家の御殿を明治期に移築したもの。

本丸西虎口。
大きく綺麗に加工された石材が積まれており、高さもあります。
本来は石垣の上に多聞櫓が上がっていて、石垣の間には埋門形式の門がありました。
残念ながら多聞櫓も埋門も消失。

西橋から見た本丸石垣と天守台。
現在は天守台石垣のみが残りますが、天守には後水尾天皇が二度も登ったそうです。

北土蔵。
漆喰の壁が剥がれており、損傷が大きいように思えますが、重要文化財なのでその内修復が入るかもしれませんね。

北中仕切門。
90度に折れ曲がって、食い違いの虎口になっており、埋門形式の門で本丸北側の東西を仕切っています。

鳴子門と奥に見えるのは桃山門。
防御を重視した門というよりは、格式を意識した門とされています。

そして、桃山門。
奥に見えるのは鳴子門。
桃山門も城門としては、これまた珍しい長屋門形式。だいたい長屋門は城下町の屋敷などで使われています。
築城年月日が不明らしいので、当時は長屋門では無かった可能性もあります。

続いて南中仕切門。
切込接で積まれた立派な石垣の中に、北側と同様に東西を仕切る門が設けられています。
規模、構造共に北中仕切門と同一です。
しかし、南中仕切門の石垣は周りが整備されているので、美しい姿を見ることができます。

屋根の造りが特徴的で、片側だけ一般的な屋根のように伸びているこのスタイルは、招造と言われています。

南中仕切門の手前からは天守台石垣、本丸石垣と中仕切門の石垣が複雑に織りなす芸術的な写真を撮ることができます。
個人的にはこの写真が好きです。

本丸東側から撮影した天守台。
芸術的に反った天守台石垣。この上に建っていた五重の天守は、きっと美しかったに違いありません。
天守台の周りには木が生い茂っているため近くで綺麗に撮ることはできません。
天守台を撮るなら、桃山門の脇からか本丸西虎口の西橋上からがベストです。

城内からみた南門。
南門は江戸時代からあった門ではなく、大正4年に大正天皇即位の饗宴が二条城で行われた為、天皇の入場口として設けられました。

場外から見た南門。
橋は取り外されています。

続いて西門。外堀石垣をくり抜いたような埋門形式。
かつては木橋が架けられていましたが、現在は取り外されています。
二条城の西側はこの西門を通過すると、本丸の目の前の為、内部は枡形と櫓門で厳重に防備されていました。

二条城最後の門は北大手門です。
北大手門は門は空いてますが、こちらから入城することができないので、ゲートが閉まっています。
東大手門よりは一回りサイズダウンしますが、一般的な櫓門形式の城門としては大きい方なので、是非見て頂きたいですね。
ちなみに、二条城の外堀を一周すると1.9kmになります。

最後に二条城に現存している二つの櫓を紹介。
東大手門に近い東南隅櫓。
さすが将軍家の城。
二重構造の櫓でありながら威厳と威圧が伝わります。
1602年〜1603年に建築。
1626年に改修されました。

続いて、西南隅櫓。
二条城には城郭の四隅に同じような櫓が配されていましたが、1788年の大火で多くの櫓が消失してしまいました。
唯一残ったのが、この西南隅櫓と東南隅櫓となり、共に国の重要文化財です。
長方形の石落としが屋根の軒下まで伸びています。方形の綺麗な形で設計されているのを見ると、やはり二条城はただの軍事施設ではなく、美を追求した誰かに見せる為の城だったのかなと想像できます。

西南隅櫓と東南隅櫓は姿形や大きさが似ていますが、破風に明確な違いがあります。
東南隅櫓は三角形の千鳥破風でしたが、西南隅櫓は唐破風です。
破風一つで印象がガラリと変化します。
屋根の隅の跳ね上がりを見ても芸術的で美を感じます。
初めての二条城でしたが、かなり充実した時間となりました。
多種多様な門があるので、一つの城でこんなに堪能することは他ではなかなか出来ません。
当然、豪華絢爛な二の丸御殿も素晴らしかった。
石垣も築城当時の最高技術を結集したものと思われます。二条城は重要文化財が多いので、建築物に目が行きがちですが、大迫力の石垣も必見です。
歴史の転換点はこの二条城から。その中心を感じることができる、素晴らしい城でした。