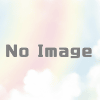【大阪府】大坂城(再訪)

2025年6月25日
昨日の岡山県から大阪府に移動し、本日も朝イチに城巡りです。
7時半に森ノ宮駅側の駐車場に到着。そこから歩いて大手門側へと向かいます。
大阪城は超巨大城郭なので、大手門の反対側となる森ノ宮駅からだと、かなり歩きます。
前回行った時はあまり時間がなかったので、外堀の石垣を見ることができませんでした。
今回は昨日の岡山城と同様に、大坂城の石垣を中心に見て周りたいと思います。

まずは南外堀の石垣です。
屏風折れの高石垣と現存の一番櫓。
朝早くにも関わらず人が多いのですが、皆さん早々に天守へと向かっています。大阪城に来たら南外堀は必見です。

美しい曲線美の隅石。
水堀に映る逆さ石垣も良い感じで撮れました。
奥に見える高層ビルのコラボは、ビックシティ大阪市のど真ん中に位置する大阪城らしい風景。
朝早いこともあり、空気が澄んでいて清々しい。

どの角度からでも迎撃できるように、石垣が屏風のようにいくつもクランクしてあります。
死角を極力減らすための防御システムです。
ここまで迫力ある石垣は、他の城ではなかなか見る事ができません。

南外堀の石垣の高さは、基礎となる根石から30mと全国で二番目の高さを誇ります。
この高石垣に残る現存櫓は六番櫓。
1628年に創建され、重要文化財に指定されています。当時は一番櫓から七番櫓まで立ち並んでいましたが、現在は一番櫓と六番櫓のみが残っています。

東側から撮影した南外堀。
いくつも折れ曲がった屏風折れの石垣。圧倒的な高さだけではなく、芸術的な技術。
鉄壁の防御施設は、現代ではアートとして我々の心を掴み続けます。

いよいよ大手門から主郭へと入城します。
日本一来場者が多い城の大坂城ですが、早い時間なので人がまだ少ないので良い写真が撮れます!

大手門の左手には千貫櫓と多聞櫓が現存します。

千貫櫓の石垣はせり出しているので、大手門から攻めてきた敵を横から攻撃する役割がありました。
また大坂城の正門にある櫓なので、唐破風や千鳥破風など装飾美と格式を感じます。

大手門を抜けると巨大な枡形になっており、90度折れ曲がって櫓門形式の多聞櫓が待ち構えます!

この枡形の大きさにも驚かされますが、規格外の石垣を最初見た時は衝撃を受けました。
石垣というより、もはや岩です!

ちょうど下に置かれているコーンを見ればその巨大さを感じることができます。
巨石の形に合わせて綺麗に合わせ込んだ、間の石も技術を感じます。

鉄板で覆われた重厚感のある門です。

内側からのショット。
多聞櫓を支える石垣も、門の柱も他の城では見ることのできない独特な凄みを感じます。
大手門の枡形に限らず、大坂城の石垣には石と石の間の目地に白い物が詰まっているのが分かります。
これは城壁と同じ漆喰で、江戸城も同じように石の目地には漆喰が塗られていました。

大手門を抜けると本丸を囲む空堀を見ることができます。
外堀の石垣は広い水堀から見るので、間近で見ることができませんが、本丸の石垣は割と近くで見ることができます。
隅の算木積みは特に圧倒的な大きさ!めちゃくちゃカッコいいです。

本丸に向かうと南仕切門跡を通過します。二の丸を西と南で仕切っていた門。

南仕切門には太鼓櫓があり、緊急事態の際に鐘を鳴らす役目がありました。大坂城では一番小規模な櫓で、明治維新の大火で消失。

太鼓櫓跡を過ぎると、素通りしてしまいそうになる程小さく石碑が立っています。
石山本願寺の推定場所とされていて、豊臣秀吉がこの地に大坂城を築く前は、石山本願寺がありました。
石山本願寺は寺でありながら幾つもの堀を巡らせ、高い土塁や塀を築いた鉄壁の要塞で、さらに武装した門徒衆によって守られていました。
織田信長は石山本願寺と10年以上戦い、この地を手に入れますが、その後本能寺で討たれます。そして豊臣秀吉がこの地に巨大城郭の大坂城を築くことになります。

石山本願寺の石碑の奥には、二の丸から見た六番櫓を近くで見ることができます。
先ほどは外堀から眺めましたが、近くで見ると大きくて立派な櫓です。

六番櫓に連なる石垣の上端には、石の切り欠きを見ることができます。

これは銃口を差し込んで敵を攻撃する石狭間と呼ばれるもの。
当時は石狭間の上には土塀や櫓になどが設けられていました。

大坂城の至る箇所にこの石狭間が造られています。
ちなみに、この石狭間は大坂城、江戸城、二条城、岡山城でしか見ることができません。その中でも、特に大阪城はこの石狭間の宝庫といえます。

いよいよ本丸に通じる桜門にやってきました。
門の奥には大坂城天守も見えています。
見どころは左右の巨石!
本来、何個もの石を積み上げて石垣を形成しますが、超巨大な石材が使われていています。これは龍虎石と呼ばれ雨が降ると右に龍、左は虎が現れると言われています。

桜門前から見た本丸石垣 右側。
水堀を張り巡らせた大阪城ですが、ここだけは空堀となっています。

桜門前から見た、左側の本丸石垣。やはり隅角石がエグいほど大きい!

桜門は高麗門形式で重要文化財に指定されています。
明治維新の大火で消失しましたが、明治20年に陸軍によって復元されました。

桜門を抜ければ巨大な枡形になっており、大坂城の見どころの一つとなる蛸石を見ることができます。
本丸直結の門となるため、蛸石以外も使われている石の大きさが別格に大きい。

至る所に巨石が使われている大阪城ですが、その中でも一番大きな石はこの蛸石になります。
左側の模様が蛸に見えることから、蛸石と名付けられました。
蛸石は岡山藩が運んだと伝えられており、表面積は36畳!重さは106トン。ワタクシの部屋6つ分よりも大きい。

桜門枡形のもう一つの門跡にも規格外の石が使われています。
元は蛸石の上には多聞櫓、この門跡には櫓門がありましたが、残念ながら明治維新の大火で消失。

まるでテトリスのように綺麗に切った石が、隙間なくビシッと積まれています。

角に使われている石は縦長で、一つの石で最頂部まで伸びています。
これは他の城では見たことがありません。
今回は天守のある本丸には向かうことなく、ここで引き返して本丸東丸側の石垣を見に行きます。

本丸南側の空堀にそびえ立つ石垣の隅石。
美しい勾配と、巨大な石で形成された算木積みは大阪城の特徴。
現在の大坂城は、大坂夏の陣で勝利した徳川が天下普請で造らせた城なので、担当大名によって積み方や石材の産地が異なります。

本丸南側は空堀、東側は水堀に切り替わります。

こちらは一番櫓。
玉造口から攻めてくる敵を迎撃する役割がありました。
二層二階 高さ14.3mで、貴重な現存櫓。創建は徳川幕府再築工事の最終フェーズとなる1628年とされています。

本丸東側の石垣は幾つも折れ曲がり、攻めてくる敵の死角をなくして攻撃できるように工夫されています。
当時はそれぞれの角に三層三階の櫓が上がっており、櫓間は多聞櫓で繋がっていました。
残念ながら空襲で消失してしまいますが、当時の写真が残っています。

南側から北側にかけて、大坂城は緩やかな下り坂になっているので、奥に行けば行くほど石垣が高くなっています。

本丸東側の石垣は本当に高くて、今まで見たことのないほどのスケールです。

そして本丸東側石垣の端部は、日本一の高さを誇る32m!
ビル10階くらいの高さ。水面までは24m、水の深さが6m、根石が2mとなります。
水深が6mというのも驚きですけどね。
このとてつもないほど高い石垣ですが、勾配も美しく芸術的なのです。ワタクシが撮ったこの角度からの勾配が特に綺麗に見えます。

この圧倒的スケールの高石垣に上がっていた三重櫓を、実際にこの目で見てみたかったものです。

大坂城にある4つの出入り口の一つとなる、青屋門。
本丸東側の高石垣が一番近いのは、この門となります。
本来は多聞櫓で繋がっていました。

立派な門ですが、青屋門は明治維新の大火で消失。
その後、陸軍が復元するも大阪の空襲によって再び消失。現在の門は1969年に当時の残材を使って再建されました。

青屋門から東側の外堀に出ます。
東側外堀は幅が80m近くありそうな、かなり広大な水堀となっています。
豊臣の時代から徳川の時代が来たことを知らしめるための城でもあったので、幕府は全てにおいて2倍という数値で改築しました。
そこで高石垣や巨石など、他の城で見ることのできない独創的で、スケールの大きな城に仕上がりました。
京橋口方面の散策は次回また来た時に行きたいと思います。
今日は2時間ほど歩きましたが、ほんの一部しか周る事ができませんでした。
今回で二回目の訪城でしたが、まだまだ見るべきところが満載です。大坂城を本当に堪能するのであれば、1日は絶対かかるのではないでしょうか。
また近いうちに、訪れたいと思います。